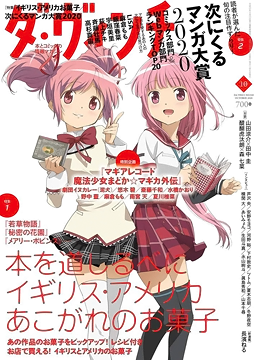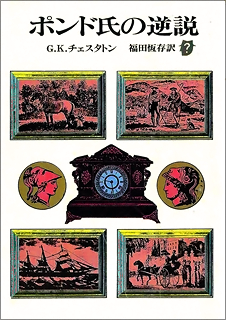新田次郎「アラスカ物語」(昭和49年)を読む。新潮文庫平成20年51刷で読む。BOで110円で購入して6年積読だった。
明治元年、東北石巻の医家に生れた安田恭輔。15歳で両親とも失い、長男と次男はなんとか医学の勉強ができたのだが、三男恭輔のころには父が連帯保証人になっていたせいで山林田畑を売ってしのぐようになり家が傾く。淡い恋も失う。
そして三菱汽船石巻支店に就職。そして船員としてアメリカへ。東洋人として差別され農奴のような生活。そしてアメリカ沿岸警備船にコックとして乗り込みフランク安田となる。
ベアー号はエスキモー部落を襲撃強奪する海賊船(こいつらが酷い)を取り締まるための警備船。だが、氷に閉ざされ身動き取れなくなる。順調に海面を走っているうちは船員の誰も東洋人に目もくれなかったが、手違いと不正により6カ月あるはずの食料が2カ月しかないという状況がわかると、疑いと憎悪の目がフランクに向く。
この船にいると自分はリンチに遭うかもしれない。頭が良く有能なフランクのことを理解してくれた船長に、自分が単身で南にあるアラスカ・ポイントバローへ徒歩で救援要請に向かうと告げる。これはほぼ見込みの少ない自殺行為。
頭上で輝くオーロラをなるべく見ないで雪原を歩く。わずかな食料しかない。極地方ではコンパスはあまりアテにならないが、ときどき方位を確認しマッチを擦り、星を見てだいたいの感覚で南へ。やがて幻覚幻聴。だがエスキモーの犬橇に発見されポイントバローへ。現地交易所に駐在するチャールス・ブロワー氏と出会う。
食料を積んだ救助が向かう。フランクは英雄だが、かつての自分の船室はすでに荒らされている。以後、船を降りブロワー氏をたよってポイントバローでの生活。
ブロワー氏の仕事を手伝うためにエスキモーの言葉を覚える。そのためにはエスキモーたちの生活へ溶け込む必要が…。
19世紀末から20世紀のエスキモー社会がほぼ古代。客人に妻(年をとってる場合は息子の嫁)を客人にふるまうだとか、シャーマンの予言で漁の占いだとか、イグルーのトイレが個室になってなくて臭いが酷いとか、江戸明治日本人が忌み嫌った土人の風習。白人がやってきて鉄や銃をもたらすまでほぼ石器時代。
頭の良いフランクはエスキモーの言葉を覚え、鯨に銛を撃ちこみ活躍し、ときに占いで不吉だからと追い出されもしたのだが、やがてポイントバローのエスキモーたちのリーダーのような存在へ。
エスキモー娘ネビロ(初恋の千代に似ていた)と結婚し娘も生まれる。フラックスマン島交易所も任される。
だがエスキモー集落は鯨が捕れないとすぐに飢餓の恐怖。海獣を乱獲し密漁捕鯨をする海賊が野放しのせいで鯨が回遊してこない?
米政府の支援で小麦、大豆、玉ねぎが届くのだが、エスキモーたちは生肉を食わないとやっていけない。
フランクが狩ってきた獲物もリーダーに許可も挨拶もなく勝手にすべて貪り食われたときは、フランクも呆れる。こんな未開人種は有史以前から滅亡を繰り返してきたんだろう。
さらに、白人が持ち込んだ麻疹でポイントバロー500人のうち120人が死んでしまうという大惨事。フランクのひとり娘も幼くして死んでしまう。
ポイントバローから見て南側にブルックス山脈がある。フランクは猟の腕を見込まれて砂金採り山師カーターに仲間として加わるよう求められる。金鉱が見つかれば権利を山分け。この男にうさんくささを感じていたのだが、悪党に命を狙われたときに命がけで助けてくれた。こいつは武士道を持っているに違いないと参加を決意。
ジョージ大島という日本人と出会う。この人はインディアンの言葉が話せる。
ジョージは白人に不信感を持っていて、フランクに忠告アドバイス。カーターはジョージを嫌う。
しかし、カーターもジョージも正直でいい人。ジョージの尽力で後にフランクとアラスカインディアン大酋長との間に、ポイントバローのエスキモー移住交渉がまとまる。
さらにジェームス・ミナノという日本人とも出会う。広大なアラスカで三人の日本人が出会ったことは奇跡。日本を遠く離れたアラスカでみんな苦労したようだ。(上州出身のジョージは日系人収容所で亡くなったらしい。出身地も不明なミナノについては農業をやった後にフェアバンクスでコックをしてたらしい。新田次郎がこの本を出版した後も何の情報も寄せられなかったとのこと。)
アラスカの山と沢を歩き回り、ついにフランクは、ネビロの偶然の発見から、シャンダラー河で多くの砂金のある場所をつきとめた。カーターへ急いで知らせる。暗号をつかって。この時代にアラスカに入っている砂金採りはほぼみんな浮浪者のようなもので粗暴。いさかいや略奪、殺人も起こってた。用意周到にカーターは権利を確保してシャンダラー金鉱の経営に乗り出す。
そしてフランクはポイントバローのエスキモーの移住を本格化。
だがそこはインディアンの勢力圏。インディアンってエスキモーを生肉を食うからと忌み嫌う。エスキモーはインディアンを恐れる。両者にはそんな敵対関係があったって今日まで考えたことなかった。
あと、エスキモーは樹木の存在は知っていても実際に見たことがなく、エゾマツの臭いに強い抵抗を示す…という箇所が意外だった。
アザラシからとった脂で灯明を静かに燃やすエスキモーは、薪を燃やして焚火も初体験…という箇所も興味深かった。
仕留めた野生動物をその場で切り開いて生のまま食べるエスキモーが、ムースの肉は臭くて生で食べない…という箇所も意外。氷点下40度で暮らしてた人々が氷点下20度の世界に来ると寒暖差にやられて風邪を引くとか意外。
シャンダラー金鉱もやがて終りがやってくる。フランクは毛皮取引に活路。野生動物に頼る産業は動物が減ると危機を迎える。やがて農業経営にも手を出すのだが船は持っていなくて失敗。
ビーバー村の古老となったフランク。日露戦争も第一次大戦も関係なくアラスカの自然と戦っていたのだが、日本とアメリカが開戦したことのみで逮捕され飛行機に乗せられ収容所へ。アメリカは酷い。今も酷い。
しかしフランクの人柄を知る人々から当局には多くの嘆願書。
アメリカに渡りアラスカにたどり着き、生涯で一度も日本に帰ることのなかったフランク安田90年の生涯。巻末に新田次郎せんせいの取材ノート的なあとがき。石巻の安田家の当主女性が検察事務官でとても冷たい対応でびっくり。新田先生以前に取材に来たジャーナリストがとても失礼だったとはいえ、人気作家だった新田先生にけんもほろろでびっくり。



























.png)