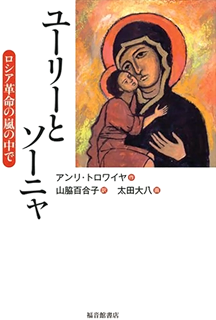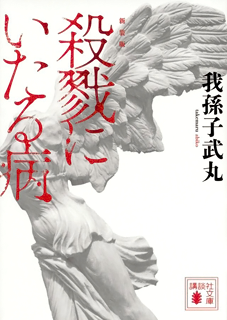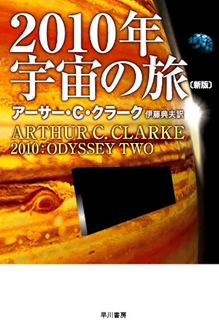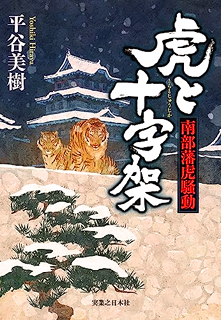アンリ・トロワイヤ「ユーリーとソーニャ」(1992)山脇百合子訳、太田大八画、福音館書店(2007)を読む。
これは括りでいうと児童書?漢字のほとんどにフリガナがふってある。おそらく小学高学年以上向け。
山脇百合子って「ぐりとぐら」の絵を描いた人?!
アンリ・トロワイヤ(Henri Troyat 1911-2007)は現代フランスの作家だが本名をレフ・タラーソフというロシア人。幼少時にロシア革命を逃れてパリに移住。19歳より作家活動。
これ、図書館廃棄処分本だというのでもらってきた。あまり読まれた形跡がないキレイな本。読んであげないともったいないので読む。SNS上でもあまり読んでる人がいない。
ロシア帝国モスクワから約100km、トヴェリ県クフシーノヴォのサモーイロフ家はなめし皮工場を経営する裕福な一家。この時代のロシアは田舎でも電気が通ってたのか。
1916年クリスマス、父の帰りを待つユーリー少年11歳が主人公。小間使いドゥニャーシャには父親が誰かわからない娘ソーニャ(11)がいる。母はこの小間使いを気に入りソーニャを家族同然に扱う。
家庭教師の婦人がいるのだが、ユーリーはこの怒った顔をした堅苦しい性格の悪い家庭教師が嫌い。進歩的な思想を持っていて皇帝を批判してる左派。
ドイツとの戦争で物資が不足。馬は軍にとられて痩せた馬しかいない。それに父親の工場では日に日に労働者の不満の声。皇帝はすでに退位。ボルシェヴィキ勢力が強まっている。ペトログラードのケレンスキー政府ももう持ちこたえられない。
赤衛隊が当局の命令だからと勝手にサローイモフ家の林の木は切り倒されるし、工場監督は殺され吊るされるし、家宅捜索されるし(あの家庭教師が密告か?)、父は人民の敵として告発され連れていかれるし、家も接収されるし、皇帝とその家族はエカテリンブルクで処刑されたと聞くし。これがロシア革命のときの有産階級がたどった道か。
小間使いドゥニャーシャが有能だし交渉上手。執事と父を取り戻す。何もできない母に代わって通行証や鉄道切符を手に入れる。心づけを渡して粗暴なボルシェヴィキ男たちを手なずける。
そして母、小間使い、ユーリー、ソーニャはゆっくり鉄道で10日以上かけ、父の待つハリコフまでの旅。
列車が農民たちで超満員だし、体臭が酷いし、トイレもない。食事は自分たちでなんとかしないといけない。途中で取り調べを何度も受ける。衣服に縫い付けてある紙幣や宝石がバレないか心配。ニコライ二世の肖像を持っていた男は途中で降ろされ銃殺。
これがロシア革命の混乱。レーニンは罪深い。ボルシェヴィキもその支持者もみんな品がなく粗暴。今のロシア人はこんなやつらの末裔。品のある人々は殺されたか海外へ逃げた。
大人たちはみんな暗い顔だが、ユーリーとソーニャはどこか非日常を楽しんでる風。
ドゥニャーシャがとにかく有能だしたくましい女性。ナイフをちらつかせる危険な酔った男を夜の間に始末する。当局に見つかったらどうする?「男が1人増えようと消えようと何の問題もない」他の乗客もなんとも思わない。
機関士が途中の野原で列車を停止させ、乗客を棄ておいてそのまま帰宅w もう自分の仕事を続ける理由もない。ま、社会が変革するとき誰もが自由。
ドゥニャーシャが次の駅まで歩いて汽車を動かせる人を連れてこようと提案。居酒屋にいた飲んだくれ元機関士見習い老人を連れてくる。なんというコミュ力。
ウクライナは二つの勢力が争ってる。しかもドイツ軍もいる。途中から鉄道の線路が取り払われていてもう先へは行けない。まるでカオス。
そこに地元の馬車が裕福な客を求めてやってくる。だが、そんなものに乗って大丈夫か?
御者が「近道だから」と他の馬車と違う近道を行く。やっぱりドイツ軍につかまる。鉄条網の収容所へ。
さらに酷い境遇。スペイン風邪が蔓延中で母も感染。薬もない。うわごとを言うようになる。これは相当にヤバい。なのに子どもたちは自由に遊び回る。楽しそう。
ユーリーはドイツ兵と知り合うのだが、この人はユーリーと同じ年の子どもを残してアルザスから出征。ドイツ人を憎んでる。収容所内でウォッカを密造。ユーリーの母がスペイン風邪と知って、「スペイン風邪にはウォッカが効く。だが値が張る。」という。ドゥニャーシャに相談すると、その額なら払えるという。
待て待て、そんな代物に残り少ない金を使ってしまって大丈夫か?と思ってたら、母は快方へ向かう。あのドイツ兵は詐欺師じゃなくてよかった。
だが、衛生上の理由でこどもたちは全員丸刈り命令。坊主頭になってしまったソーニャをドゥニャーシャは慰める。「ターバン帽をつくってあげる」
やっとのことでハリコフに着くと、そこにいるはずの父がいない。ホテルにいくと置手紙。ボルシェヴィキ警察から逃れるためにオデッサへ行ったらしい。
親切な紳士の協力で必要な書類を手にいれ、さあオデッサへ出発。だがその直後に列車は脱線。どんだけ試練が続く?!
フランス軍が駐留するオデッサで父と再開。え、ユーリーとソーニャは恋?
子どもなのに裸になって抱き合ったり?!ここ読んで児童向けとしてどうなの?って思った。ユーリーはソーニャにプレゼントする本を万引きしてるし。(ここ、日本の少年少女向けにするならカットしてもよかった)
だが、ユーリーが盗んだ本を贈り物にするという箇所は、ずっとサモーイロフ家のために尽くして有能ぶりを発揮したドゥニャーシャの最後での悪女な振舞と対になってるなと感じた。そこに気づける児童っている?
現実リアルでビターな結末。この本、やっぱり大人向けじゃん。
読んでいてスピルバーグ映画「太陽の帝国」を思い出す内容と構成だった。
実質ヒロインといっていい未婚の母ドゥニャーシャが、まるで「崖の上のポニョ」のおっかさんで脳内再生していた。絶望的な状況であっても諦めないし逞しい。
てか、この本を福音館さんはもっと本気でがんばって売って欲しい。なんならジブリアニメにならないか?宮崎駿翁はこういう女性が好きだろ。