THE ODESSA FILE by Frederick Forsyth 1972
この本のオデッサとはウクライナの港町のことではない。元SS(ナチ親衛隊)隊員の組織を表すドイツ語「Organisation Der Ehemaligen SS-Angehörigen 」の頭文字を繋ぎ合わせた造語。なので日本語訳にするなら「ナチス親衛隊残党ファイル」とすれば間違いなく意味が伝わったかと。
敗戦の屈辱と困難は一般ドイツ人に押し付け、自らは大量の金塊を持ち出し海外へ逃亡し自由な生活を送る元隊員たちを再びドイツ国家の中枢と要職に戻し、現在行われている元ナチ党員らへの問責は不当であると一般ドイツ国民に宣伝したい。それがオデッサの使命。
フォーサイス氏はこの本を書くために元SS隊員に取材したのだが、取材協力した人々から名前を公表することは拒否された。
ケネディ大統領が暗殺された同じ日の夜のハンブルク。ジャガーを乗り回すやり手のフリージャーナリストのペーター・ミラーは、アパートでガス自殺した老人が搬送される現場に居合わせる。
このタウバー老人がナチス占領時代のラトビア・リガのユダヤ人収容所で看守をやらされていた。地獄のような虐殺の日々を生き残った。自分はあの日以来もう死んだも同然。
手記を残したけど、同じようなものはもうすでにたくさん発表されている。いまさら世間も注目しない。だが、看守だったロシュマンの冷酷な微笑は忘れない。ぜったいにナチスを弾劾する法廷に立たせたい!
この60年代当時、イスラエルはアイヒマン裁判を世界に中継。あと残された最重要お尋ね者はマルティン・ボルマンとヨーゼフ・メンゲレ。
英国人作家の書いたこの本では、ロシュマンはメンゲレ以上のランクのお尋ね者という設定。
エアハルトとベングリオンとの西独とイスラエルの武器供与契約に怒り心頭のオデッサ。戦争に負けたとはいえ、西独にはまだまだイスラエル人を「ブタ野郎!」と罵るような已然メンタルはナチ野郎がたくさんいたらしい。
イスラエルと敵対するエジプトをドイツの伝統的友人として支援するオデッサ。コードネーム・バルカンというロケット技術研究者に近づくやつは何が何でも阻止。
ミラーはタウバー老人唯一の友人マルクスを探し当ててエルベ川辺のベンチで話を聴く。生前にタウバーが「ロシュマンを見かけたことがある」と話してた。野心的ジャーナリストのミラー「こいつを探し当てて法の裁きを受けさせたい!」
英国人フォーサイスが描く60年代ドイツ人たちの戦争とユダヤ人虐殺への罪悪感が興味深い。この時代のドイツ人たちは「あれはポーランドやチェコのような遠い場所で起こった自分たちとは無関係な不幸な出来事」「学校では習うけど、積極的に知りたいとは思えない。」と考えたかったらしい。
50代の母は息子が誰も求めていないナチスの過去を掘り起こすことに反対。仕事をもらう新聞社の上司からも「そんなの読者は求めていない」「ドイツ人はフランス人やスペイン人やソ連人よりもユダヤ人に寛容だった。誰もがユダヤ人の知己はいた。ヒトラーが出てくるまでは…」そうだったのか。
日本の場合、アジア各地の現地で捕まったBC級戦犯がいちばん過酷な目に遭った。国内で子どもたちを兵士として送り出した教育界、特高刑事たちはとくに罰っせられることもなかった。それはドイツも同じだった。甘々な対応。
戦争犯罪を起訴する担当は各州の検事長。十分な証拠があってやっと警察が逮捕できる。そのへんのことは「アイヒマンを追え!」という映画で見た。ナチの戦争犯罪訴追にがんばっても政官財と市民から白い目。
SSの戦争犯罪者の捜査はシュトゥットガルト北方15マイルにあるルートヴィヒスブルクにあるツェントラーレ・シッテレこと通称Z委員会。ここの刑事になると出世はできないらしい。予算は雀の涙らしい。
ドイツもナチスの戦争犯罪に関わった人が多すぎて、どこかで線引きしてなあなあで済ませるしかなかった。ドイツ人はみんなナチスの責任追及に消極的。出版マスコミも脅迫や広告の取り下げなど嫌がらせを受けるので消極的。
ミラーはアウトバーンをすっ飛ばしてベルリンへ。米軍の資料を閲覧。英軍が閲覧した記録がある。なのに裁判はされていない?
資料のコピーを受け渡ししていたそのときオデッサのメンバーがロシュマンの資料を閲覧していた若い男がいると上司に報告。以後、ミラーは近辺を調査される。嫌な予感。
ミラーはボンの英国大使館から英軍管轄地区で戦争犯罪裁判に関わったラッセル卿を紹介されロンドンへ飛ぶためにケルンへ。そこでオデッサメンバーから最初の警告。「調査をやめろ。後悔するぞ。」「きみも同胞じゃないか」
(ボンが西ドイツの首都になったのはコンラート・アデナウアーの故郷だから?!)
ウィンブルドンでラッセル卿に面会。ロシュマンは別の名前で投降し捕虜収容所にいたのだが1947年に釈放。ロシュマンを探していた老ユダヤ人が発見尾行。英軍に逮捕されていた。ソ連の別案件で証人として輸送中に逃亡。以後不明。
ロンドンからウィーンへ。ホテルでシモン・ウィーゼンタールに面会。こちらが調べたロシュマン情報を伝える。ウィーゼンタール氏もロシュマンを追っていた!(この本、有名な人物の多くが実名で登場)
収容所を生き延びたウィーゼンタール氏は、29歳のドイツ人青年ミラーに虐殺に関わった組織について正しい知識を講釈。
6000万ドイツ人全体に罪があるとする考え方は、もともと、連合国で生まれたものですが、元SS隊員たちにとってまことに都合のよい理論なのです。というのは、全体に罪があるという考え方が流布されているかぎり、だれも特定の殺人者を追求しない、少なくとも真剣に努力しようとしないからです。
ドイツ人は戦争責任をナチスに押しつけたと聞いていた自分は目からうろこ。
ハンブルク警察も検察庁も偉い人たちはみんな元SSだったと知らされて唖然。そりゃあ消極的なわけだ。(ドイツで裁判ができないなら、こういった本で元SSたちを告発するしかないか)
ナチスの重要人物に関する知識はだいぶ増えたつもりだったのだが、SS中将ブルーノ・シュトレッケンバッハという人物については初めて名前を知った。ナチス残党のアルゼンチン逃亡を手助けしたアロイス・フーダル司教という人物も初めて知った。
ミュンヘンでリガの生存者を探す。ユダヤ人地域センターへ。そこでリガの生き残りでロシュマンを追っている男と接触。指定された場所へ行くと目隠しされ車に押し込まれる。ユダヤ人たちのSS狩り組織のオデッサ逆スパイになるよう説得。
過去に潜入した者は爪を剥がされ運河に浮かんだ。もう一人は跡形もなく消された。でもそれはユダヤ人だから失敗した。ドイツ人の君ならできるよ!
元SS隊員から元SSらしく見えるように厳しい訓練を受ける。「ホルスト・ヴェッセルを歌えるようにしよう」これはもう明らかに深入りし過ぎだ…。
終戦時に19歳だったSS曹長になりすます。でも、向こうも知らない小物の新メンバーは警戒するのでは?あまり質問にすらすら澱みなく答えると逆に怪しいのでは?
だが、あまりにあっけない処から身バレ。電車で移動する約束なのに、ミラーは自慢のスポーツカーを運転してるところを目撃されてしまう。逆に追われる展開。アホか!
オデッサの殺し屋マッケンゼンが切れ者。さすが元SSなので即席で時限爆弾を作ってミラーのスポーツカーにセット。
興味本位で元SSとイスラエルの戦いに闖入してしまったジャーナリスト青年の運命やいかに?!
大胆無謀ミラー青年の予想外の行動に諜報のプロたちが双方で慌てふためく。オデッサ・ファイルとは何だったのか?ミラー青年の真の目的は?意外な展開。意外な結末。
結論から言って、「オデッサ・ファイル」は「ジャッカルの日」と同じぐらい傑作。天才的に面白い。今もまだ読む価値を失っていない。なんなら映画として今リメイクしたっていい。












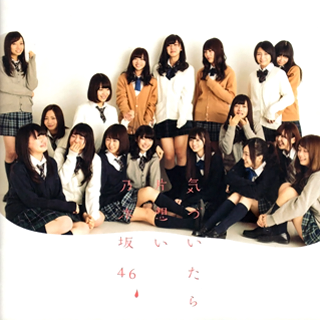


.png)




































