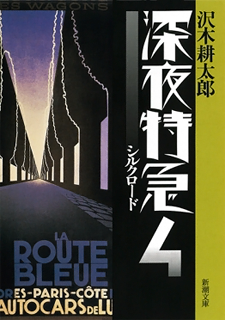遠藤周作「決戦の時」(1991)を講談社文庫(1994)版上下巻で読む。織田信長を描いた歴史小説。
自分、ぜんぜん織田信長に詳しくない。だいたい司馬遼太郎「国盗り物語」とNHK大河ドラマで得た知識しかない。
これ、1990年ごろには鮮度があった「武功夜話」という「ほぼ偽書」に全振りして魔王織田信長や藤吉郎、蜂須賀小六、そして信長が愛した女性として帰蝶(濃姫)、さらに生駒吉乃を登場させている。
自分、今まで信長には内田有紀や川口春奈や綾瀬はるかみたいな妻がいるんだとばかり思ってた。「麒麟がくる」では濃姫には帰蝶という別名があったんだ…と初めて知った。と思ってた。
だが、歴史書では「斎藤道三の娘と結婚した」という以上のことはなにもわかっていないらしい。
末森城で織田信秀(享年42)が亡くなるというところから語られる。跡目は正室土田御前が生んだ長男三郎信長が順当。
だが、この長男が品がなく粗暴でうつけ。信秀の死は3年秘匿したい。
家老の林通勝も柴田権六も母土田御前も心は信長の弟である信行を織田家の統領にしたい。
織田一門は岩倉城の織田と、清洲城の織田に別れている。織田同士が尾張の土地を争ってる。
もう序盤からネズミのような顔をした薬売りとして藤吉郎が登場。信長と今川の最初の小競り合いを見物した段階で、信長の力量を見抜く。
信長は15歳で斎藤道三の娘濃姫(14)と結婚しているのだが、生駒屋敷の吉乃という9つ年上女性のもとへ通ってる。それは濃姫と斎藤道三には秘密。
吉乃という女性について自分は今までまったく知らなかった。遠藤周作せんせいは武功夜話という前野家から最近見つかった古文書資料から、この女性像を創出してる。この女性が嫡男信忠を産んだことにしてる。(濃姫には子がなかった)
那古野城の信長は斯波義統とその守護代織田信友、坂井大膳の清洲城を攻める。このとき林通勝は信行の助力で信長が勝ったことにするために出陣を遅らせる。そのことは信長も気づく。このころこからもう信長と林通勝には心の隙間。
織田信友を攻めて自刃させた功労者の叔父織田孫三郎信光を信長は謀殺。
末森城の柴田勝家と林通勝と信行と、清洲城の信長は戦ったことがあるって知らなかった。あの短気で粗暴な信長がよく柴田と林を許したなと思ったけど、織田はまだまだ内憂外患で国内で敵をつくりたくなかったようだ。
さらに、信長は仮病をつかってお見舞いに来た弟信行も謀殺。酷い。これには13歳年下の幼い妹お市(美少女)も兄(美少年)を殺した怖い兄信長に恐怖とショック。
次の敵は岩倉城の織田信賢か。となると背後に斎藤義竜がいる。道三は死んだし、子のない濃姫はもはや利用価値がないから美濃に返そうか。というときに濃姫が自害?!(麒麟がくるとはまるで違う展開)
あっけなく岩倉城は落ち、尾張は信長のもの。だが、今川義元がいよいよ京を目指す。
今川軍が駿府から三河、尾張へ進むルートはどこか?もっとも山が迫り隘路となっている場所を藤吉郎は蜂須賀小六に調べさせていた。え、桶狭間の合戦のアドバイスをしたのは藤吉郎?
そして下巻。信長は家臣たちにも考えを明かさずに、桶狭間で今川義元を討ち取る。これには家臣たちも信長を見直す。
以後、今川は急速に力を失う。三河の松平元康は今川から離れ織田と同盟。織田は斎藤義竜に備えるのだが義竜は急死。
犬山城を攻めるいくつかの件、遠藤周作も「武功夜話」に書いてあることが「本当かどうか疑わしい」としてる。疑いつつ多く引用。だって他に記録がないから。
信長が生駒屋敷に住まわせた最愛の妻吉乃は体調がすぐれず小牧城に移したが間もなく死亡したらしい。そのへんも「武功夜話」。
遠藤周作は小折町の久昌寺を訪問。「武功夜話を編纂した吉田龍雲氏に御教示いただいて、吉乃の墓をやっと発見した時の悦びは今でも忘れられない。」と書いている。(それ信じていいのか)
小折町の久昌寺は一昨年2021年に取り壊し。まじか。生駒家の菩提寺で檀家もいなくて、建物を維持できずどうしようもなかったらしい。
そして木下藤吉郎の墨俣城築城の話。これは遠藤先生も創作説があることを断りつつ、必ずしもすべてが創作とはいえないかも…という立場。
下巻は美濃征服。後半は浅井・朝倉との戦い。浅井長政とお市の男児を捜し出して殺させた信長の極悪非道。それに加担した藤吉郎。たぶんみんな地獄に落ちてる。
次の敵は武田勝頼。秀吉はどう戦うかを信長に進言。
あと、ずっと蜂須賀小六とコンビを組んでた川筋衆の前野将右衛門親子のその後を簡単に語ってこの小説は終わる。
この小説、武功夜話が偽書ということになって、今では読む人があまりいない。