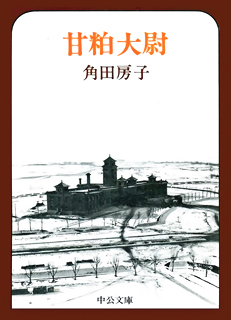前作の「ドラゴン桜」(2005)から16年ぶりの続編「ドラゴン桜」(2021)全10話を完走した。
噂が出始めたのが一昨年の秋頃。TBSはこのころから当代きっての人気俳優ふたり、阿部寛と長澤まさみに打診し始めていたらしい。
だがコロナ禍によって、生徒たちを集めた教室シーン撮影が困難になり、企画は流れたかにみえた。多忙なまさみが今更このドラマに出るとは考えにくいと思った。
しかし実現した。今回の「ドラゴン桜」が実現したのは多くの人々の努力のおかげ。
2005年版の再放送があったり、生徒役キャストを小出しに発表するなどの話題作りプロモーションを経て第1回放送をリアルタイムで見た。
2005年版は今でも伝説のドラマ。出演者の多くが今も人気俳優女優。今回の2021年版はややキャストの豪華さにおいて劣るかな…と思いながらも見た。
前作で受験当日に母が倒れ入学試験に参加すらできなかった水野が弁護士として学園再建にやってくる…という胸アツ設定。
当時18歳だったまさみは34歳に。当時41歳だった阿部寛さんは57歳になった。
美少女まさみはスーツ姿のキリッとした美女になった。端正なワイルド美青年弁護士桜木は…細くなってさらに荒くれた印象。何かの仕事に挫折して野宿したり釣したり?なにしてんの。
この龍海学園高校が偏差値32なわりに生徒たちがそれほど荒れてない。服装も髪型もちゃんとしてる。不良な感じはしないしチャラい感じもしない。ギャルもいない。時代の変化を強く感じた。今の子はじつにルールだけは守る。
そして、ちょっと失望した。つまんない…。前回の軽妙な感じがない。制作会社と演出家が変わったので仕方ないかもだが。
なんだこの半沢直樹テイストは?学園売却?黒幕が暗躍?そんな要素要らない。それに、GTOみたいにもなってる。
そもそも前回のドラゴン桜は金曜夜10時枠。今回は日曜夜9時枠という違いもある。
前作と同じものを作っても…という作り手の気持ちはわかるが、結果、期待したライトなものと違って多くの視聴者が困惑。
江口ひろみさんの理事長がおかしい。教育に強い理念を持っているから東大特進クラス創設に反対?たかだか5人ぐらいの実験的企画ぐらいなら試してみてもいいだろ。東大進学者5名出したら理事長を退任とかいう設定もあまり納得いかない。
校長がちょい同性愛者ふうに描かれてるのもちょっと嫌。
それに地域最低偏差値私立高校の生徒から東大に行けそうな子を5人選抜できるとかありえないように感じた。だからこそマンガやドラマにできるのかもだが。
特進クラスメンバーの子たちの抱える問題がヘビーに感じた。
実家のラーメン店が闇金から金を借りてる設定の瀬戸(髙橋海人)。そんなの学園に弁護士がふたりもいるんだからすぐに相談しろよとイライラした。
バドミントン選手岩崎(平手友梨奈)は顔も怖いが親もサイコパスみたいで怖い。自身の夢を娘に押し付ける親。特別料金もかからずに特別な教育プログラムを受けさせてもらえるならラッキーと思えよ。
バドミントン仲間もコーチも悪質。見ていてイライラしたエピソードなのでこの箇所はしっかり見ていない。前作ドラゴン桜と明らかに作風が違う。
さらに、学年トップ生徒小杉(志田彩良)。もうすでに模試の段階で合格圏内。そんな生徒が東大に進んだとして、どこにドラマになる要素が?
この子の父親が一番異常。女に学歴は要らないという強い信念。高校を卒業させたら結婚させる…という決意を持ったおかしな親。
こういう人は学園関係者、教師、弁護士たちが並んだ会議室で持論をまくしたてる勇気なんて持っていないはず。そんなことをすれば恥をかく。普段はしれっと普通の人のふりして常識的見解をのべつつ自分の意のままにするはず。
さらに昆虫にしか興味を示さない原(細田佳央太)。通常なら普通高校に通えないレベルの生徒のように見えた。この子が実は数学や理科、英語が一般生徒以上にできることが判明する回があった。
ネットで「感動した!」とか言ってる人も多かったようだけど、それ、そうだったらいいな♪という理想とフィクションだから!
仮に入試をパスして大学に通うとして、すべてのルールを理解して指導教官にも気に入られ研究者となっていくには相当に高いハードルがあるはず。むしろその後がさらなるドラマになるはず。
天野(加藤清史郎)はほとんど印象がない。普通の常識のある真面目生徒。前作の奥野(中尾)に相当する生徒。弟が優秀という悩み。
そして今回の最大の収穫といっていいキャストが早瀬(南沙良)。ネットをザワつかせるほどの美少女。大評判。
ごく一般的な家庭で育ったふつうにカワイイ女子生徒。軽いノリで特進クラス。とくに東大に行く理由もない。それほど深刻な悩みもない。
前作で言ったらヒロイン水野に相当するポジション。バカで素直で明るい。1回ダメな例となって、言われたことを素直に妄信して受け入れる。大人たちにとって一番理想的な生徒だし社員。国家にとっても望ましい市民。
2005年版では真面目な水野ですらちょいギャルだった。JKというものはみんなカーディガンを着てるものだと思ってたら、いつの間にか時代はスウェットトレーナーJKがキテたの?!
この子がすぐムカついたり、褒められていい気になったり、悩んだり笑ったり、普通の女子高生すぎて逆に難しいという役。
南沙良、完全にノーマークだった。今どきのカワイイ子ではあまり見ないタイプ。アジア人らしさあふれる顔。
ニコラモデル出身でレプロ所属。ガッキーと同じ道。TBSへのレプロバーターだが、次の出演作が楽しみな注目の若手女優へと躍り出た。
そして今回のドラゴン桜において生徒役でもっとも共感を呼んだキャラは藤井(鈴鹿央士)だったと感じた。こいつが初登場した瞬間から性格が悪い。態度が悪いw
自分は頭がいいと思っている。バカ高校に入ってしまったのはたまたま運悪くインフルエンザになったから。周囲の目を見返すためにも東大に行かなくては…という強い動機。先生をバカにするなど周囲に対して強がった間違った態度。
一見ひ弱そうなガリベン秀才に見えるのだが、カラダがでかくてチンピラ風生徒にも当たりで負けていない。むしろこいつがイジメる側。今回のドラゴン桜で一番しっくり納得がいくキャラ。思うように結果が出なくて悩む。
鈴鹿央士という若手俳優は「蜜蜂と遠雷」に出てた。広瀬すずにスカウトされたという逸話を持つ美少年だったのだが今回のドラゴン桜で大きく存在感が増した。結果、7人の生徒の中で一番目立ってたのは藤井。
藤井が対決に負けて「じゃあな藤井、もういいぞ」「バイバイ藤井」とか言われる(イジられる)シーンが最高に可笑しかった。藤井に「いさせてください…」と言わせようとする女子たちが真正のどSだったw
育ちのよさそうな早瀬が藤井に対しては口が汚いのも笑った。「よく来れたね?頭打った?」とか「むかつく!ムッツリ野郎!」とか。
第1話から登場するチンピラ男ふたり組はドラマが進むにつれだんだん人気が高まってきたキャラ。(まだ俳優の名前を覚えるまでには至っていない。すまん。)
あれだけ質の悪い反社工作員チンピラだったのに、死ぬほどビビらされてすぐに桜木の舎弟。こいつらの行いと顔を見れば「そんなタマじゃねーだろ」と思わずにいられない。
乗せられて東大受験勉強まで始めてしまうという、ちょっとリアルさに欠ける便利な存在のマンガキャラ。
そして長澤まさみ。今回は自分が生徒たちを立てて導く脇役的存在であることを理解しつつ、そのようにふるまい、存在感を出す超一流の女優。まさみと共演できた生徒たちにも強い刺激になったであろう存在。生徒役の子たちはまさみの活舌のよさと声の大きさに驚いたそうだ。さすがだ。
桜木の授業の補助教員的役割だったのだが、第9話では弁護士として奮闘し、相手の汚いやり方に怒りで震える…というようなシーンはあった。
そもそも大規模リゾート開発のための土地買収っていまどき何言ってんの?そんな景気のいい話あんの?昭和バブルの廃墟リゾート地が日本各地で骸をさらしている。そんな計画に銀行は金を貸すの?
東大数学の鬼・柳先生(品川徹)との16年ぶりの再会に胸アツ。品川さんも16年ぶりの再登場。お変わりなく元気そうでなにより。ただ、前作からの再登場先生は柳先生のみ。前作は先生たちのキャラもマンガっぽくてよかった。今回の講師たちはゲスト的登場のみ。
今回、マンガっぽいキャラで強いインパクトを残したのが現代文(のちに古文も担当してることが判明)の太宰府先生(安田顕)。この人が出てきただけで笑ってしまった。
英語担当特別講師由利杏奈(ゆりやんレトリィバァ)はわりと常識的。それほどのインパクトはなかった。だが、英語記述式問題の書き始め定型文には感心。こういうの、知ってるのと知らないのとでは大きな差。自分は試験問題見てからその場で考えてた。公平な条件じゃなかった。
理科・社会にいたっては特別講師どころか先生役すらいない。そんなんでいいのか?
いや、高校を卒業するために必要な単位の授業は?そういった箇所はまったくなかった。
さすがにもう受験勉強裏技知識のようなものだけでドラマを10話つくれない。今回「マジカルバナナ」があったものの、それほど役に立ちそうもない。もっと視聴者といっしょに考えてみるような問題を出題してみてもよかった。
結果、第2話まではつまらないな…と感じていたけど、第3話以降はそれなりに楽しめた。そもそも長澤まさみという女優を地上波連続ドラマで見れること自体が貴重。ただ、黒スーツ以外の普段着水野が少しでいいから見たかった。
最終回の会議室シーンが時代劇みたいだった。思わぬ助太刀と復讐劇。今回嫌だったのがこういった半沢っぽいシーン。
山Pとガッキーを投入してくるとか、なりふりかまわない視聴率爆上げ作戦。とくにまさみとガッキーが手を繋いでるシーンは泣いた。16年ぶりの共演シーンに。