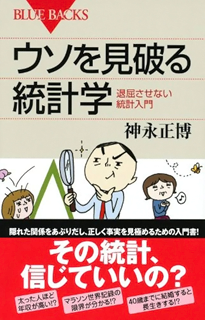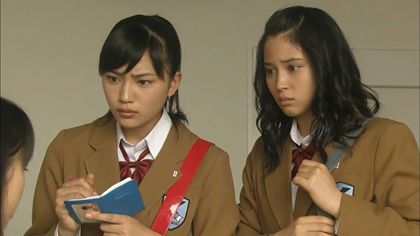8月19日・26日放送の「鶴瓶の家族に乾杯」は海外スペシャル。2週に渡って鶴瓶師匠とゲスト本田翼がマレーシア・ペナン島(ジョージ・タウン)できまぐれに歩き回って人々に凸。これは6月24日に収録したらしい。
たぶん、多忙な師匠も本田も、事前にマレーシアの知識を勉強する時間もなかったに違いない。短時間の滞在だったに違いない。
まず、鶴瓶師匠と本田翼というコンビが、ばっさーオタならついエモくなる組み合わせ。かつてTBS「A-studio」で毎週MCをやっていたペア。
当時20歳だった本田翼の何がすごいかって、鶴瓶師匠に対してもタメ語だったということ。さすがだ。愛嬌さえあればなんでもできる。
マレーシアはマレー人、中華系、インド人による複合多民族国家。異文化イスラムで家族に乾杯って、ゲームとマンガしかやってない本田翼にはハードル高すぎないか?
師匠といっしょに街を散歩。本田の最初の挨拶が「スラマッパギ!」
そこにあった道教寺院に参拝。管理してるおばさんがわりとビシバシ厳しく、師匠の参拝マナーを指導。師匠も本田とMCやってたときから10年以上経ってて72歳。だいぶ髪の毛もなくなったな…。
その一方で本田はあまり雰囲気が変わらない。
本田は単身になると同年代か若い世代と話をするべく、若者がいそうな場所を求めて歩く。
この番組は本当に行き当たりばったり。事前にスタッフが若者がいそうな場所とか何も調べてない?
そもそも東南アジアの人々は暑い日中はほとんど出歩かない。(日本も夏は夕方4時から出勤し23時台に帰宅するように考え方を変えるべき)
ちなみに、本田翼はハトの群れが苦手らしい。いや、それは誰もが苦手かもしれない。
街のアイスクリーム屋の店員に話しかけるとパキスタン人。なんと本田と同じ年。そこにあったモスクにも入ってみる。観光客女性は肌の露出を隠さないといけないので、フードのついた上着を貸してくれる。女子学生によるコーランの詠唱に目を丸くする本田。自分もまだ一度もモスクには入ったことがない。
マレーシア人はドリアンだいすき。自分は幸いなことにまだいちどもドリアンを食べたことも臭いをかいだこともない。
今回の本田の最大の試練が、お屋敷町の豪邸に突撃訪問をすること。本田も「渋谷の松濤でピンポン押すようなものですよね?!」とビビる。
NHKはそんなことをさせるのか?それって下手をすると外交問題にならないか?
だが、そこは一流の愛嬌を持った美人本田。たまたま香港系で親日的な、子ども連れの若い奥様を引き当てた。車で帰宅してきて門を開けるタイミングでインタビュー交渉。
ふつうなら断られるはずだが、本田の服装身なりや美貌を瞬時に値踏みしたのかもしれない。この若奥様の豪邸がすごすぎる。そして多少は日本語知識もあった。日本にも行ったことがあった。
後日、本田翼のインスタアカウントをチェックして330万人フォロワーもいるインフルエンサーモデル女優だったことを知り驚いた子どもたち。
あとは、空港からバスで市街へ向かう途中にあって気になったという路地を散策。地元民若者と触れ合ったり。いや、危ない場所とかに紛れ込まなくてよかった。マレーシアにはそれほど危険なスラム街とかはないのかもしれない。
いや、本田翼に感心しかしなかった。さすがの愛嬌力と美貌力。